はじめのひと吹きに、いつも妙な緊張をしていました
フルートを始めたばかりの頃は、息を入れる瞬間まで「今日は音が出るかな…」と、毎回ちょっと構えてしまっていました。
出るときもあれば出ないときもあり、その差は自分でも予測がつかず、最初の音が鳴るまで少しドキドキしていたのです。
そんな不安定さを少しずつ減らしてくれたのは、「音が鳴る仕組み」と「自分の体の使い方」を知ることでした。
息の流れ、唇や顔まわりの筋肉、そして体全体の姿勢や重心。
これらをひとつずつ見直していくことで、最初のひと吹きに対する構えや緊張も、少しずつ和らいでいきました。
音が出る仕組みを、ちゃんと知ることから
私自身、あるとき「音が鳴る仕組み」をあらためて学ぶ機会がありました。
それまでは、なんとなく音が出ていて、深く考えたことがありませんでした。
「どういう角度で息が当たると音が響くのか」
「楽器のどこにどんな風に空気が流れているのか」
そうした基本的な“仕組み”を知ったことで、吹き方が変わってきたように思います。
さらに、口の形や唇まわりの筋肉の使い方にも目を向けるようになりました。
私の場合は、頬をほんの少し引き上げるようにイメージすると、音の流れがスムーズになってきました。
とはいえ、それがすぐにできたわけではありません。
むしろ、それまで使っていなかった筋肉を意識することで、最初は疲れることも多かったです。
でも少しずつその感覚に慣れていくと、力みのない自然なアンブシュアへと近づいていきました。

音が出ない原因は、唇だけじゃない?
音が出にくいとき、どうしても「唇の形」や「アンブシュア」だけに意識が集中しがちです。
でも実は、身体全体のバランスや使い方が、音の出やすさに大きく影響していることも多いのです。
たとえば、
・息を吸おうとしたときに肩が上がっている
・肘や手首に力が入っていて、楽器を不自然に支えている
・無意識に重心がどちらかに傾いている
・息を支えようとしてお腹が固まり、逆に呼吸が浅くなる
こうした「体の中の見えない力み」が、息の流れを妨げたり、音の方向を不安定にしたりする原因になることがあります。
私自身、うまく音が出なかったときに「お腹が固まっていた」「肩が上がっていた」と後から気づくことがありました。
そうした“自分の癖”に目を向けることで、音の通りが少しずつよくなっていったと感じています。
姿勢は「静止」ではなく「流れのある安定」
姿勢というと「まっすぐ立つこと」と思われがちですが、
私が意識しているのは「動ける余白のある安定した姿勢」です。
演奏中は、音楽の流れに合わせて体も自然に微細に動いています。
そのとき体に無駄な力が入っていると、息の通り道も狭くなり、音も閉じてしまいます。
私はレッスンで、「丹田(おへその少し下)」に重心を落とすように意識して立つと、身体全体の力がうまく抜けて、安定した息が出しやすくなる、という話をすることがあります。
「姿勢=止まること」ではなく、「支えながらも呼吸と響きが流れること」
そう考えると、演奏の感覚も少しずつ変わっていくように思います。

原因を知ると、次の一歩が見えてくる
音が出にくいとき、「自分には向いてないのかも」と落ち込んでしまうこともあるかもしれません。
でも、音が出ない=失敗ではありません。
むしろ「出にくい」という現象の中にこそ、自分の吹き方や癖、体の使い方について見直すきっかけがあると私は思っています。
・息を入れても音にならない → 息の方向が下がりすぎているのかも
・音がかすれる → 唇や手首に力が入りすぎているかも
・高音が出ない → 息のスピードや方向性の見直しが必要かも
そんなふうに、「なぜ?」を一つずつ丁寧に見ていくことで、
次の一歩が、少しずつはっきりしてくるように思います。
基礎の基礎こそ、音づくりの土台
私が大切にしている基礎練習のひとつに「ソノリテ」があります。
これは音を一つずつ丁寧に鳴らし、その響きを確かめながら進めていく練習です。
ただ音を並べるのではなく、
「今出した音はどんな響きだったか」
「次の音へどうつなげたいか」
そんなふうに、一音一音と向き合っていくこと。
シンプルに見えて、この時間が音の土台をつくり、息や体の使い方を整えてくれると感じています。
音が出にくいときほど、急がずこの基礎に立ち返ることが、結果的に一番の近道になることもあります。
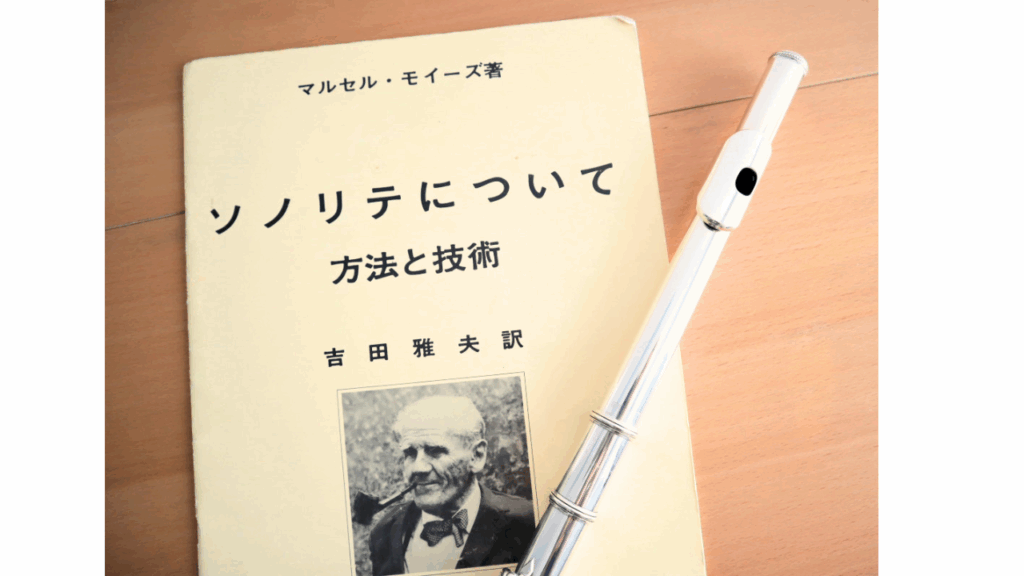
レッスンで大切にしていること
レッスンでは、「今どこに力が入っていそうか」「どう吹こうとしていたか」を
一緒に言葉にしていくことを大切にしています。
・音が出たとき、どんな感覚でしたか?
・息はどこへ向かっていたでしょう?
・肩や手は、自然に使えていましたか?
こうした問いかけを通して、自分の身体と心にある“気づき”に耳をすませていく。
その積み重ねが、無理なく自然に音とつながる土台をつくっていくと感じています。
音が出なかった日も、意味のある日
音が出なかった——それは、がっかりすることかもしれません。
でも私は、そういう日こそ「何がうまくいかなかったか」「どう吹こうとしていたか」に目を向けてほしいと思っています。
練習とは、“できること”を積み重ねるだけではなく、
“気づけること”を少しずつ増やしていく時間でもあるからです。
音が出にくい日は、「何かに気づける日」でもある。
そんなふうに考えられると、気持ちも少し軽くなるように思います。
最後に|うまく吹ける日は、きっと来ます
最初は音が出なかった私でも、いまこうしてフルートを教え、演奏する立場にいます。
だからこそ、今「音が出にくい」と悩んでいる方にも、伝えたいのです。
できなかったことが、できるようになる日は、必ず来る。
そして、ただ音が出るだけでなく、
“自分の音が好きになれる”日も、きっとやってきます。
焦らず、今の自分の音と、静かに向き合っていきましょう。
その一歩一歩が、確実に音の未来を変えていきます。


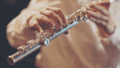

コメント